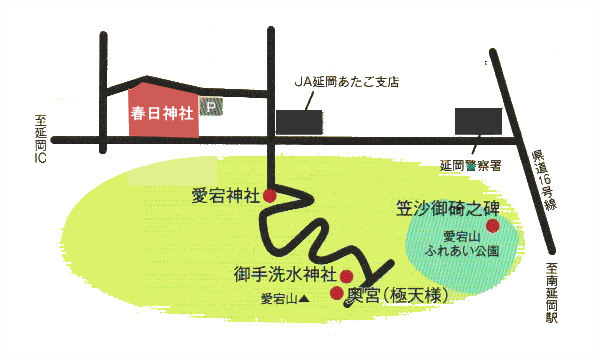春日神社御由緒
当社の御祭神、天児屋根命・武甕槌命・斎主命(経津主命)・姫大神は、日本国の成り立ちに深く関わられ、邇邇芸命が日向の国高千穂久志布流峰に天下り給いし時の随神英傑の神々であり、上古よりこの地に斎い奉り来て、荒瀬宮と申し上げていました。
今から1300年程前、大納言惟資(これすけ)が、神殿を建立し、春日大明神と尊び敬って名付け、この後の領主、土持・高橋・有馬・三浦・牧野・内藤の歴代各藩主は、篤い尊崇の念を持って多くの寄進を惜しまず、領民達もこぞって参詣しました。
廃藩後の明治4年7月、社号が「恒富神社」と改称されましたが、氏子の熱望により、昭和43年、古来の社名「春日神社」に復元し、春日さんと親しまれながら現在に至って おります。
社殿の両側に天高くそびえる楠の御神木は、向かって右側のものが、幹回り10メートルを超え宮崎県下7番目、左側のものが8.5メートルで18番目の巨樹です。いずれも樹齢900年にも及ばんとし、60余種の樹木と共に、みごとな神奈備の杜を形成しています。
なお、大己貴命・事代主命・保食命・武南方命・土持兼重霊神が合祀されています。